心不全
心不全とは
心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、体内の必要な組織へ十分な血液を送り出すことができなくなった状態を指します。単なる一つの疾患名ではなく、さまざまな心疾患が最終的に至る共通の病態を表す言葉です。そのため、心不全は「状態」であり、多くの病気の進行の結果として現れる症候群とも言えます。
心不全は大きく分けて、「急性心不全」と「慢性心不全」に分類されます。急性心不全は突然心機能が悪化し、命に関わる症状が現れることが多いですが、慢性心不全は徐々に心機能が低下し、日常生活に支障をきたすようになります。慢性心不全も、再発や悪化を繰り返すことで、急性増悪を起こすことがあります。
欧米では、心不全は非常に頻度の高い疾患であり、1,000人あたり約7.2人が罹患していると報告されています。日本でも高齢化や生活習慣の欧米化が進む中で、今後患者数はさらに増加することが予測されています。現在すでに130万人以上が心不全の診断を受けており、将来的にはさらに深刻な国民病となることが懸念されています。
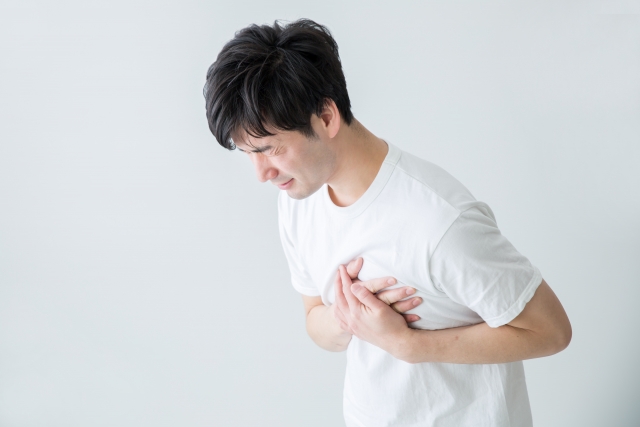
心不全を起こす疾患は?
心不全を起こす要因には幅広く多様な病気があります。
心筋の異常
- 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)
- 心筋症(肥大型心筋症、拡張型心筋症など)
- 心毒性物質(アルコール、抗がん剤、抗不整脈薬など)
- 感染性(ウイルス性心筋炎、細菌性心筋炎など)
- 免疫疾患(関節リウマチ、多発性筋炎など)
- 内分泌疾患(甲状腺機能亢進症、クッシング病など)
- 代謝性疾患(糖尿病など)
血行動態の異常
- 高血圧
- 弁膜症
- 心外膜炎
- 貧血
- 腎不全
不整脈による異常
- 頻脈性不整脈(心房細動、心室頻拍)
- 徐脈性不整脈(洞不全症候群、房室ブロック)
心不全の治療
心不全の治療で最も重要なのは、原因疾患を適切に見極め、それに応じた治療を行うことです。たとえば、狭心症や心筋梗塞が原因であればカテーテル治療、弁膜症が原因であれば手術による弁形成術や弁置換術が必要になることがあります。原因疾患に対する根本的なアプローチなしに、心不全そのものをコントロールすることは困難です。
その一方で、心不全の進行に伴って生じる症状や体内の変化には共通点が多く、それらに対しては標準的な薬物治療が確立されています。特に慢性心不全では、心臓の負担を軽減し、症状の悪化を防ぐことを目的とした複数の薬剤を組み合わせた治療が中心となります。

慢性心不全
- ACE阻害薬
- ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)
- β遮断薬
- MRA(ミネラルコルチコドイ受容体拮抗薬)
- 利尿薬
- 血管拡張薬
- ジギタリス
- ICD/CRT
- 心臓リハビリテーション
